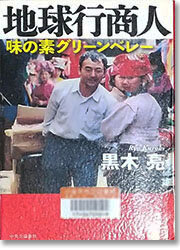 中央公論新社★
中央公論新社★
これは失敗。世界をまたにかけた感動もののセールス成功物語かと思ったら少し違った。「東南アジア切り込みセールス成功セールス事例集」みたいなものでした。
「ベトナム△△市、▼課の鈴木一郎は蒸した暑さに汗をふいた。鈴木はがっしりした体格で身長は170cmほど、短くした髪は・・・・」てな調子。ま、苦心してセールスのコツをつかむんですね。その章がおわると次は「カンボジア南部▼市の郊外。△△は途方にくれていた。小袋がまったく売れないのだ・・・」とか。同じパターン。
なるほど大変なんだな・・・とは思うけど、それだけ。飽きます。もちろん入社した新人はぜひ読んだほうがいいですね。ただ部外者はあまり感動しません。
そうそうに挫折。
夜中にふっと目が覚めて、どうでもいいこことをダラダラ思い出すことがある。ややこしいこともあるけど、なんせ夢うつつです、なるべく単純なこと、たとえば古い歌の歌詞とか。
たとえば「Oh my darling Clementine」のこととか、「絵もない花もない居酒屋」とか。
昨夜はなぜか「十七、八のねえさんが」だった。えーと、てまり唄でしょうね、一かけ二かけて三かけて......とか。記憶のなかでは橋の欄干に十七、八のねえさんが腰かけていて「わたしは九州鹿児島の西郷隆盛娘です」と名乗る。なんか筋がまとまらない。
 十七、八のねえさんが腰かけて、はるか向こうを眺めるのだったかな。ん、これも整わない。
十七、八のねえさんが腰かけて、はるか向こうを眺めるのだったかな。ん、これも整わない。
珍しく日中に思い出して、調べてみました。唄なんでバリエーションはいっぱいありましたが、たとえば『下松市の民話・伝説と民謡』版では
一かけ二かけ 三かけて 四かけ五かけ 六かけて
橋の欄干に腰かけて 遥か向うを眺むれば
十七八の姉さんが 片手に花持ち 線香持ち
お前はどこかと問うたれば
わたしゃ九州鹿児島の西郷隆盛 娘です
『鳥取博物館』版では米子市富益町の採集として
一かけ 二かけ 三かけて 四かけて 五かけて 橋をかけ
橋の欄干手を腰に はるか向こうを眺めれば
十七、八のねえさんが 片手に花持ち 線香持ち
もしもしねえさんどこ行くの
わたしは九州鹿児島の西郷隆盛 娘です
けっこう違うんですね。でも筋は論理的になりました。橋の欄干に腰かけて いたのは姉さんじゃなかった。十七八の姉さんが橋の欄干というのはけっこう絵になると思っていたんですが。残念。
肩の痛みは継続。だんだん慣れてきました。期間がながくなったので、モーラステープの消費量がすごい。ま、我慢できなくなったらまた整形へいく予定。ヒアルロン酸の注射は確かにききます。
先日は子供に誘われて劇団四季。ライオンキングです(※)。ま、行ってよかったというべきかな。よく工夫された演出ですね。ただ二階席は予想外の急傾斜がすごい。手すりなんかの配慮はあるけど、足腰に自信のなくなったトシヨリには少し恐怖です。つまずいたら転げ落ち・必須で、もし一階まで落ちたらたぶん、死ぬ。
眉の下にできてちょっと目障りだった(もう10年近くになる)ニキビのなれの果て。皮膚の余り。決心して取ってもらうことにしました。液体窒素かなんかを使った処置です。
あっさり終わるかと思ったら計算違い。何週間かはかかるらしい。ま、しかたないですね。毎週通っています。少しずつ少しずつ組織を殺していきます。あとどれだけかかるか。それまでは瞼の上に黒いかさぶたが乗っている。けっこう間抜けです。
※久しぶりの有明。すっかり雰囲気が変わっていました。ずいぶん清潔そうで、都会的な街になっていました。何十年ぶりになるんだろ。
時々やってるWizardry8。実はここ1週間ほど「武器の自動入れ替え(持ち替え)」で悩んでいました。
 つまり短い剣かなんか持って戦っているとき、敵がこちらから離れることがある。「逃すか!」ってんで背負っていた弓に持ち替える。
つまり短い剣かなんか持って戦っているとき、敵がこちらから離れることがある。「逃すか!」ってんで背負っていた弓に持ち替える。
これ、ふつうは自動で入れ替わります(※)。ところがこのところ、これが何故かできなくなった。うーん。困る。もう弓は使わないにするしかないのか・・。
さんざん困って、悩んで、念のためにプログラムファイルを総入れ替えまでしたんですが、そのタイミングでついに判明。
図の部分です、新発見の機能。ここで「交換 Lock / Unlock」を設定するらしい。で、それに偶然さわってしまってたんでしょうね。不要の機能のような気がするけど、自動交換なんて絶対したくないユーザーがいるのかもしれない。
ゲーム始めてから24年にして、初めて知った機能です。まったく奥が深いというか、アホというか。
※写真の場合なら剣(接近戦)と弓(遠距離攻撃)が持ち替わります
駅前の眼鏡屋で購入。家用。ほんとうは5000~6000円程度でいいと思っていたのだけれど、結果的には9800円。ま、いいでしょう。
 実はこの店では数年前にも安物を買っていて、これは焦点を近くに設定しすぎて失敗。もうどのメガネがいいのか混乱模様の訳わかめなんで、7~8年前に新宿で買ったすこし高いの(一応は大事にして外出用)と度を合わせてもらいました。たぶん使えるはずです。
実はこの店では数年前にも安物を買っていて、これは焦点を近くに設定しすぎて失敗。もうどのメガネがいいのか混乱模様の訳わかめなんで、7~8年前に新宿で買ったすこし高いの(一応は大事にして外出用)と度を合わせてもらいました。たぶん使えるはずです。
しかし、1時間待って作ってもらった今回のも、長くかけていると左目がすこし疲れてくるみたいです。メガネって、難しいものですね。
スーパー店内の通路で立ち止まって「はて次は・・」とか考えていたら、手に持ったメガネの玉がコロリと外れて落ちた。
このところ落ち癖のあった古メガネです。でもよりによってこんなところで・・。下でペッと跳ねて、大きな冷蔵ケースの下へ。2センチくらいあった隙間にきれいに滑り込んだ。あらら。
店のおっさんに一応は(ダンボールの切れっぱし使って)下の隙間を軽くさらってはもらったけど、ま、無理です。冷蔵ケースは大きくて奥行き1メートル以上はあるし、たぶん奥まで転がっている感じ。こりゃ届きませんんね。見えない。引っかからない。諦めました。
仕方ないです。外出用のメガネの度を計ってもらって、同じデータで新しいのをつくるか。家用ですね。使いやすくてなるべく安いのがいい。明日にでも駅前へいく予定。ほんとに、まったく。
肩と手首の痛みはまだ治らない。そろそろ2カ月近くになるのかな。半分諦めています。神様か仏様が「そろそろ放免にしてやるか・・」と思いつかない限りダメでしょう。ま、そうはいっても原因不明の痛みの通例、多分あと2~3週間もすれば自然治癒と思っています。
で、通院3回目になる整形クリニック、今日はとりわけ混んでほぼ3時間半の待ちでした。もうどこかで昼飯たべて帰るしかなくなったので、待合室での最後の1時間くらいは近くの店の検索でした。
 しかしまともな店だとせいぜい午後2時くらいでランチタイムはおしまいですね。結局は早い・安い・美味しい。定番吉野家です。なるほど。から揚げなんかが新メニューに加わってるのね。うーん・・と迷った末はこれも伝統定番の牛丼。たしか今回の値上げで大盛はかなり高くなってた記憶があり(※)、看板商品の牛丼並におちつきました。たぶん割安。久しぶり、おいしかったです。
しかしまともな店だとせいぜい午後2時くらいでランチタイムはおしまいですね。結局は早い・安い・美味しい。定番吉野家です。なるほど。から揚げなんかが新メニューに加わってるのね。うーん・・と迷った末はこれも伝統定番の牛丼。たしか今回の値上げで大盛はかなり高くなってた記憶があり(※)、看板商品の牛丼並におちつきました。たぶん割安。久しぶり、おいしかったです。
※牛丼大盛は税込み740円。牛丼並は税込み498円。定価改定したばっかりのせいか気のせいか、肉の盛りがよかった印象です。(写真は公式サイトから借用させてもらいました)
この冬は加湿器でずいぶん快適に過ごせました。年のせいか冬は肌の乾燥がめだってきて、数年前から購入を考えていた。ま、このての話のお決まりですが、三年ほどかけてようやく実現。シンプルなYAMAZENのスチーム式加湿器です。
 リビングの目立たないところに置いておく。朝に3リットルの水をいれて夕方あたりにはまた補給する。けっこうな量の水を消費ですね。おかげで乾燥肌で苦しむことがなかった。ありがたい。
リビングの目立たないところに置いておく。朝に3リットルの水をいれて夕方あたりにはまた補給する。けっこうな量の水を消費ですね。おかげで乾燥肌で苦しむことがなかった。ありがたい。
ようやく必要がなくなる季節になり、後始末はクエン酸を50gほど入れて30分過熱。2時間ほど冷ましておしまい。こびりついていたカルキがきれいに取れました。なめたいほど奇麗になる。
クエン酸というもの、初めて使いました。すごい。すこし、感動です。
 新Valkyrieをつくって、レベル8でRogueに転職。ほかの連中が1レベルをモゴモゴの間にもうサッとレベル8です。
新Valkyrieをつくって、レベル8でRogueに転職。ほかの連中が1レベルをモゴモゴの間にもうサッとレベル8です。
ただしStealthと鍵開け修行がきついですね。きつい。
UmpaniBaseで弱っちいダミー(ひょうきん人形)相手に延々闘ってようやくStealth50。で、鍵開けは残っていたAnnaの宝箱で修行中。これはひたすらひたすら辛抱です。現在ようやくLockスキル20。まだまだ先は遠い・・・。
※ 追記:ほぼ半日かけてLockスキルも45超え。ただここで安心して転職するとガクッと下がる。Rogueボーナスが消えるんですね。で、更におまけをつけて実質38まで上げて落着。Stealth50、Lock38。大丈夫でしょう。元のValkyrieになってDreadSpearを持ちます。やれやれ。
何年かぶり、6人パーティでWizardry8を遊んでますが、レベル13あたりで急にRogueが面白くなくなりました。盗みはうまいし戦闘も強いんですが、レベルアップの際にポイントを割り振る項目が見つからない。ここを育てよう...という部分がないんですね。なんか楽しみがない。
 数日にわたって悩んで(この悩みが実はWiz8の楽しみでもある)、Priest→Valkyrieの転職を取りやめです。思い切ってゲームを2レベルほど戻しました。で、レベル11あたりでRogueを新人Valkyrieと交代。新ValkyrieはどこかでStealthと鍵開け修行も必要。
数日にわたって悩んで(この悩みが実はWiz8の楽しみでもある)、Priest→Valkyrieの転職を取りやめです。思い切ってゲームを2レベルほど戻しました。で、レベル11あたりでRogueを新人Valkyrieと交代。新ValkyrieはどこかでStealthと鍵開け修行も必要。
したがって従来のPriestはValkyrieじゃなく、もう1レベルくらい育ててからFighterにします。HealAllを唱えられる変則(または魔道)の戦士ですか。あは。
結果的には Fighter(元Priest) / Valkyrie(新人) / Samurai / Ranger / Monk / Bishopになります。Valkyrieの発育はけっこう早いです。すぐ追いつく。FighteはTheAvengerを持つ予定です。かなり強いパーティと思います。
※おかげで右手の腱鞘炎がなかなか治らない。
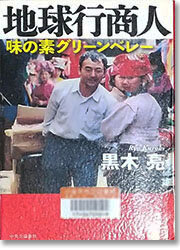 中央公論新社★
中央公論新社★ 十七、八のねえさんが腰かけて、はるか向こうを眺めるのだったかな。ん、これも整わない。
十七、八のねえさんが腰かけて、はるか向こうを眺めるのだったかな。ん、これも整わない。 つまり短い剣かなんか持って戦っているとき、敵がこちらから離れることがある。「逃すか!」ってんで背負っていた弓に持ち替える。
つまり短い剣かなんか持って戦っているとき、敵がこちらから離れることがある。「逃すか!」ってんで背負っていた弓に持ち替える。 実はこの店では数年前にも安物を買っていて、これは焦点を近くに設定しすぎて失敗。もうどのメガネがいいのか混乱模様の訳わかめなんで、7~8年前に新宿で買ったすこし高いの(一応は大事にして外出用)と度を合わせてもらいました。たぶん使えるはずです。
実はこの店では数年前にも安物を買っていて、これは焦点を近くに設定しすぎて失敗。もうどのメガネがいいのか混乱模様の訳わかめなんで、7~8年前に新宿で買ったすこし高いの(一応は大事にして外出用)と度を合わせてもらいました。たぶん使えるはずです。 しかしまともな店だとせいぜい午後2時くらいでランチタイムはおしまいですね。結局は
しかしまともな店だとせいぜい午後2時くらいでランチタイムはおしまいですね。結局は リビングの目立たないところに置いておく。
リビングの目立たないところに置いておく。 新Valkyrieをつくって、レベル8でRogueに転職。ほかの連中が1レベルをモゴモゴの間にもうサッとレベル8です。
新Valkyrieをつくって、レベル8でRogueに転職。ほかの連中が1レベルをモゴモゴの間にもうサッとレベル8です。 数日にわたって悩んで(この悩みが実はWiz8の楽しみでもある)、Priest→Valkyrieの転職を取りやめです。思い切ってゲームを2レベルほど戻しました。で、レベル11あたりで
数日にわたって悩んで(この悩みが実はWiz8の楽しみでもある)、Priest→Valkyrieの転職を取りやめです。思い切ってゲームを2レベルほど戻しました。で、レベル11あたりで