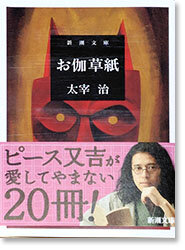 新潮文庫★★★★
新潮文庫★★★★
喫茶店での時間つぶし用に、ふと気が向いて太宰治の「お伽草紙」 を買いました。秋ごろです。たしか喧嘩名人の話とかカチカチ山の処女ウサギの話とかだったよな。楽しんで読めるはず。
で、ときどき引っ張り出して少しずつ。そうそう、防空壕で子供に話してあげるんだった。瘤取りじいさんは覚えていました。酔っ払い爺さんが鬼に気に入られてコブをとられてしまう。うんうん。
カチカチ山も記憶していました。潔癖なウサギ(たぶん処女。美少女の無慈悲)とあわれな狸のお話。みんな傑作です。高校のころは太宰が好きだったなあ。思い出した。異色では戦時の女学生日記みたいなのもあったな。あれも清冽だった。富士と月見草もそうですが、太宰は嘘がきれい。上手いです。
あれ、この浦島太郎は覚えてないなあ。舌切雀もなんか違う。で、喧嘩名人の話はない。平安美男に変貌する話もないし。。変だなあ・・・。
あらためてネットで確認。そうかタイトルがまったく違っていたんだ。自分が読むつもりだったのは「ロマネスク」でした。「仙術太郎」「喧嘩次郎兵衛」「嘘の三郎」の3話とある。これと「お伽草紙」がごちゃごちゃになってしまった。
なんか自分の記憶もとんと信用できなくなりました。なかなかに、困ったもんだ。
ずいぶん前からパソコンの電源ケーブルの差し込みが甘くて閉口していました。筐体の裏に手をのばしてちょっとケーブルに触ると接触が切れる。ちょっと真っすぐに直してやると電気が通るようになる。
3ピンのメスで、調べると「IEC C13」というらしい。これの電源ユニット側の受け(オス)が「IEC C14」です。でもなんでこんなに作りが甘いんだろ。差し込みが浅いです。危険すぎる。
いろいろ考えて、新しく差し込み部分がL字のケーブルを買いました。たぶん揺れが少なくなるはずです。アイネックスのケーブルで。コードがやけに細いのが気になりました。一応7Aまで大丈夫と表記はあるんだけど、なんか心配。(通常の電源ケーブルって何故かバカみたいに太くて硬いのが当たり前なんで)
 交換作業。コード類をぜんぶ抜いて筐体を引っ張り出す。裏側をまるだしにして、念のためもう一度古いのを刺しなおしてみました。場合によっては3ピンプラグの面取りも考えていたからです。角ばったところを削ったらスムーズに差し込めるようになるかもしれない。
交換作業。コード類をぜんぶ抜いて筐体を引っ張り出す。裏側をまるだしにして、念のためもう一度古いのを刺しなおしてみました。場合によっては3ピンプラグの面取りも考えていたからです。角ばったところを削ったらスムーズに差し込めるようになるかもしれない。
ん? スルリと入る。新感覚。奥までしっかり差し込める。なんでだ。
こんなにしっかり入るんなら問題なし。もうケーブル交換は中止です。そうか。裏側のせまいところに手をまわしてモゴモゴやってたから真っすぐ差し込めていなかったんだ。ソケットを正しく正面において虚心に真っすぐ差し込んだらなんの問題もなく奥まではいる。
今までの自分が正真正銘アホだったという結輪です。そういえばさんざん苦労の内部24pin電源 だって、まじめにやってたら何故かスンナリ(あるていど)入ってしまった。いままで悩んでいたのは何だったんだろ。
狐につままれた気分です。
PC起動時にビープ音が聞こえる。そうですね、発生は月に数回程度かな。長いのが1回、短いのが3回のビープ。で、なにごともなかったように通常起動する。気味が悪いのでたいてい再起動かけてます。
ASUSのマザーの場合、長1回短3回はビデオ関係のトラブルの可能性が大らしいです。ビデオねえ。
可能性としてはビデオカード(補助電源不要)への電力供給がギリギリであるかも。うーん、けっこう売れてるクロシコのカードだからなあ。まさかという感じ。
もう一つの可能性はモニターケーブルとかモニターのソケットとか、そのへんに軽微な問題がある場合。これも可能性は薄そうなんだけど。
というあたりで終わっていたんですが、ふとDVIとHDMIの違いを思い出しました。はい。何年か前、ビデオデッキを新規購入の際にHDMIケーブルが余ったので、ためしにその余ったHDMIケーブルをモニター接続に使ってみた。それまではDVIケーブルだったわけです。
 「DVI→HDMIの変更によって画面がかなり明るくなった」なんて書いてますね。そんなら以後ずーっとHDMIかというと、またDVIに戻している。理由は色ズレです。
「DVI→HDMIの変更によって画面がかなり明るくなった」なんて書いてますね。そんなら以後ずーっとHDMIかというと、またDVIに戻している。理由は色ズレです。
なんで色ズレが起きるのか。これも適当に「モニターのコンセントの穴がホコリで汚れていたせい」とか書いてる。そんならホコリを綺麗にしたのか。してないみたいです。「前と同じコンセント」とか変なことも書いてるし。うーん。なんかスッキリしない。
ものは試し。スッキリしない場合は試してみるに限る。モニターケーブルをHDMIに変更してみました。なるほど、確かにいまでも色ズレが再現できます(※)。
徹底的に試してみますか。
(1)モニター側のNo2 HDMIソケットにも差し込んでみました。→ 色ズレに変化なし。つまりモニター側に責任はない。
(2)HDMIソケットにエアーダストスプレー 。前回やった記憶はないけどビデオカード側のソケットにもプッシュ。これでホコリは飛んだはずです。→ でもやはり変化なし。
うーん。こうなるとあとはHDMIケーブルの交換しかないですね。あるいはビデオカードのHDMIソケット部分に問題がある。その場合ビデオカード交換。無理だべ。
使ってみたHDMIケーブルは「Hight Speed」グレードでした。品質は十分なはずなんだけど更に高級な「Ultra High Speed 」にする必要があるか。替える必要があるかないか。悩ましいところです。面白いけど、難しい。わからない。
※今回まじめにDVIとHDMIを比べてみましたが色合いの違いはわからず。ただズレだけは今回も確認できました。やはりHDMIは問題がでてますね。掲載画像は「こんなふう」と示すために色を塗ったものです。
最近はけっこうまめにXとかSNS周辺とかうろついていますが、なにやらかにやら、だんだん嫌気がさしてきました。うんざり。暗澹。明るくないなあ。
ほんと。アメリカの民主党支持者は何を思って暮らしてるんだろ。いや米国にかぎらず世界中どこでもそうですね。空が明るくない。空気がどんより濁っている。
ま、昔の中国のインテリ連中なら「竹林」とか洒落のめして釣りをするとか、本を読むとか。琴棋書画。
そうそう、よく中央で志をとげられなかった詩人なんか、故郷の月夜の湖に舟をうかべて酒をすするシーン。あれ、ずいぶんカッコいいですが、実際は違う。大きな何隻もの船をうかべて周囲には芸妓が5~6人。どんちゃんどんちゃん。酔っぱらった友人連中が3~4人。わっはっはいっひっひ。もちろん料理人もいる。ま、そんなのが現実だっただろう。なにかで読んで深く納得しました。
はて、なに書いてんだろ。
りくりゅうの逆転劇、良かったです。ただテレビつけてると同じシーンを何回も。おまけに感動の内容がどんどん細かくなるというか、解説がつまらなくなるというか。かといってチャンネル変えると見たくもない人がアップになって演説してたりして危険。あわてて電源落とす。
図書館に行かなくなってからほぼ一か月、まだ飢餓症状はあらわれていません。何もしていないけど、なんとなく1日が忙しいです。窓の外はかすかに春のきざし。もうすぐ暖かくなりますね。
暖かくなったら乱雑な机の周辺、また整理するか。エネルギーの充填待ちです。
ま、PC持ってれば否が応でもMSのOfficeは使わざるを得ないわけです。仕方ない。でも Office 365とかで毎月課金は困るなあ(※)。なんせ月々ン千円です。そんなわけで思い切ってWord 2019を買い切りにしたのが2021年でした。あらら、もう5年近くになるのか。Word、余計な機能が多すぎて非常に使いにくいのですが、それでも5年。慣れました。
あのとき本当はExcelも欲しかったです。でもWordとExcel一緒じゃ財布がむり。諦めた。
しかしなんか表計算ソフトふうのものががないと不便ですね。いろいろ探した末に使っていたのがMS Office互換で無料のLibreOffice(の表計算部分だけ)でした。はい立派なソフトなんですけけどね。ただ機能が多い。立派すぎる。それに本家のExcelとはかなり操作が違うんです。
なんかないかなあ・・とずーっと適当なのを探していたんですが、先日ついにぶちあたった。WPS Spreadsheets。どうもWPS Officeという有料の総合オフィスソフトの一部分らしい。しかしこのSpreadsheetsだけは無料です(※)。軽い計算ソフトなんで、有料版への呼び水という位置付けなのかもしれない。
 しかしこっちも必要なのはシンプルな表組レイアウトと簡単な計算機能だけなので、軽いのは大歓迎。
しかしこっちも必要なのはシンプルな表組レイアウトと簡単な計算機能だけなので、軽いのは大歓迎。
用心しいしい「無料ダウンロード」という表示からダウンロードしました。インストールすると表計算とかPDFとかいくつかの機能が可能な模様で、一瞬、有料版Officeを落としてしまったかと心配してしまった。もちろん欲しいのはExcel機能だけなので他は無視。My Documentの古いExcelで作ったファイルの数々を今回のWPS Spreadsheetsに紐づけました。開いてみるとわりあいシンプルで、使いやすそうです。満足。アイコンのデザインもそう悪くはないし。
※Office 365じゃなくて今はMicrosoft 365だそうです。勝手にしなさい。
※WPS Office2というのもあるようだし、トライアル版は無料とかの表記もある。けっこうややこしいです。ほんのごく一部だけが本当の「無料版」なのかもしれません。ダウンロードする際は記述にご注意を。販売は日本のキングソフト・・なんだけど中国系ふうでもあり、よう知らん。ダウンロードふくめて自己責任で。
これもNHK「京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-」の話ですが、各話の終わりにながれる歌(エンディング曲)が奇妙です。まるでお経。まるたけえびすに おしおいけ・・・とか、やわらかい声の呪文詠唱が続いて最後はなぜかシャンソンになる。Je suis née dans cette ville・・云々。
 たまたま出くわした解説サイトで謎が解けました。これは「わらべ唄」のアレンジだった。京の通り名を上から下にズラズラならべた唄です。たとえば「まるたけえびすに・・」は丸・竹・夷・二・・で、丸太町通・竹屋町通・夷川通・二条通・・。延々続いて最後はいちばん南の九条通で終わる。
たまたま出くわした解説サイトで謎が解けました。これは「わらべ唄」のアレンジだった。京の通り名を上から下にズラズラならべた唄です。たとえば「まるたけえびすに・・」は丸・竹・夷・二・・で、丸太町通・竹屋町通・夷川通・二条通・・。延々続いて最後はいちばん南の九条通で終わる。
東から西へバージョンもある。こっちは「てらごこふやとみ やなぎさかい・・」寺・御幸・麩屋・富・柳・堺・・。つまり寺町通、御幸町通、麩屋町通、富小路通、柳馬場通、堺町通・・。
子供のころからこんな唄をうたって、碁盤目の京都の中心部の地名を覚える。迷子にならずにすむ。なるほどねえ。
もうひとつ。解説の地図をながめていると京都には「田の字エリア」という色付き部分があったりする。なんじゃこれは?と不審でしたが、説明をよむと「四条烏丸を中心とした四区画」であることがわかります。道路に囲まれて田の字に見える。つまりは京都の中心の中心です。東京なら銀座四丁目周辺みたいなもんですかね。地価も高い。ここに店を出せれば超一人前。大きな顔ができる。
そうそう。「京都人の密かな愉しみ」でも、京都の本当の中心はどこなんだみたいなテーマがあったりします。「御所?」と思うのは部外者。何回目かでの説明では、室町の超老舗呉服屋の主人(演・段田安則)がヤマホコ町だとか言明していました。山鉾町。これも調べると「下京区の四条烏丸・室町周辺」らしい。祇園祭で山鉾なんかを出すような町です。
深く追及するとやけに奥深いものがあるんですね、京都は。ま、だからわざわざ京都人をテーマにした奇妙な連ドラができたりする。いまは五輪番組に時間を譲って休んでますが、3月からまた毎週再開だそうです。
※西陣の老舗和菓子屋のおかみが「自分たちは生粋の京都人と思ってるけど、中京・下京あたりの人はどう思っているやら・・」とか言ってました。西陣なんて中心ではないという感覚もあるらしい。この店「どんどん焼け」で焼け出されてひどい目にあったそうです。蛤御門の変のことです。当時のおかみは命より大事な菓子木型の風呂敷背負って足袋はだしで逃げた。
※上述呉服屋主人の自慢では、烏丸通にビル立てた男が、室町に空きができたと聞くと即座にそのビルを売って移転してきた。それほど「室町」は値打ちがあるという証左。京の中心は室町。思いだしたのでメモ。
忘れるだろうから、メモしとくか。あとで振り返ることがあるはず。きっと。
2026.2.8 衆院選 全国的に大雪
| 自民 |
198 → 316 |
維新 |
34 → 36 |
中道 |
167 → 49 |
| 国民 |
27 → 28 |
共産 |
8 → 4 |
れいわ |
8 → 1 |
| 減ゆ |
5 → 1 |
参政 |
2 → 15 |
保守 |
1 → 0 |
| 社民 |
0 → 0 |
みらい |
0 → 11 |
|
|
NHKのBSで1月から「京都人の密かな愉しみ」というドラマ(だろうな)をやっています。そもそもは10年くらい前から始まったもので、いまは3シリーズ目。知ってるようで知られざる京都人の行動や考え方、観光客が知らない風景なんかをを紹介するドラマ仕立 て + 京ルポ + 京料理作り。
大胆かつ不思議な構成なんですが、映像がきれいで女優さんもいい。和服も美しいし、ま、説明の難しい番組です。途中で知って1シリーズの途中から見ています。
 で、いまのシリーズ名は「京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-」です。老舗和菓子屋をどう継ぐかがメインのテーマ。ソルボンヌからきて、京都御所のすぐ隣の洛志社大学(同志社ですね)に入学した女子学生が慣れない京文化に戸惑っているところです。
で、いまのシリーズ名は「京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-」です。老舗和菓子屋をどう継ぐかがメインのテーマ。ソルボンヌからきて、京都御所のすぐ隣の洛志社大学(同志社ですね)に入学した女子学生が慣れない京文化に戸惑っているところです。
で、ようやく本題。その洛志社大の教授が渡辺謙です。講義が終わると一人だけの研究室にもどり、やれやれとお茶をいれる。くつろぎの時。
で渡辺教授、最初の回では煎茶をいれました(後では炒り番茶をいれた回もあった※)。その煎茶のいれかた。
(1)スイッチいれて小さなポットで湯を沸かす。(2)熱湯を湯呑(または専用の器)に注いでから腕時計ちらりとみる。(3)煎茶一杯分の紙袋(たぶん)中身をゴボっとフィルターor茶こしに投入。(4)適温の湯をそそぐ。(5)湯呑いっぱいの煎茶が落ちる。で渡辺謙は満足そうに香りをかいでみたり、すこしすすってみたり。
というシーンなんですが、どうもお茶一人前がはいった「煎茶パック」みたいなのがあるように見えました。細かい部分は見逃してるんですが、それをコーヒーと同様、フィルター式に淹れる。面白い。いいなあ。
しかしネットで調べてみると発見できないんですね。見まちがいだったかなあ。市場にあるのはさまざまな「ティーバッグ」だけみたいです。湯呑にいれて湯をそそぐ方式。つまりお茶を粉末にして薄い袋に包んだもの。紅茶と同じやりかたですが、あれ、正直おいしくないです。たぶん上手く味を出せないからかな、抹茶ふうのものを混入してるのが大部分。抹茶ったってもちろん本物の良い抹茶を使う訳がないんで、たぶん安抹茶。色だけ出て、下手すると茶葉をただ粉末にしただけだったり(違ってたらごめん)。
要するに簡単に正しく一人前を淹れられる煎茶ってないんでしょうね。やはり急須を使うしかないのか。
自分は少量一杯だけ飲む場合は湯呑に葉を直接パラパラと入れたりします。すこし時間をおいて、浮いてきた茶の葉をよけながら飲む。決して美味くはないけど、急須を洗ったりする手間がはぶける。でも味気ないしな。なんかイージーでそこそこな方法がないかなと思います。あの色だけ出る「抹茶」はいらない。
※ 二月に入ってからの回では、高級炒り番茶(手炒りほうじ茶)の話もありました。職人の手による高級なもの。安いのとは別物らしい。しらんかった。
「そのうちケーブルを長く」と書いたのが4日前。駅前に買いにいこうと思ってはいましたが、正直、実店舗はあんまり安くないです。貧相なケーブル1本でも1000円以上もしたり。品ぞろえも豊富とはいえないし。
 で、ついネットッショップに頼ってしまいます。こういう行動が地元店舗を衰退させるんだなあと後ろめたさはあるものの、ま、しかたない。注文して翌日に届きました。1mのLANケーブル650 円、同じく1mのモジュラーケーブル210 円。ほんとはもっと安い品がいろいろあるんですが「送料無料」が心やましくて(※)、ちょっと高いのにしてしまった。
で、ついネットッショップに頼ってしまいます。こういう行動が地元店舗を衰退させるんだなあと後ろめたさはあるものの、ま、しかたない。注文して翌日に届きました。1mのLANケーブル650 円、同じく1mのモジュラーケーブル210 円。ほんとはもっと安い品がいろいろあるんですが「送料無料」が心やましくて(※)、ちょっと高いのにしてしまった。
で、届いたケーブルを交換。でかい光電話ルーターと電話をつなぐケーブル50cmを1mに取り替え。光電話ルーターからWi-FiルーターまでのLANケーブル50cmも1mのに交換。色も従来にあわせてます。これで窮屈だったVDSLモデム、光電話ルーター、電話、Wi-Fiルーターの4つ、3D配置がだいぶ楽になりました。
こういう作業って、なかなか楽しいです。
※いつもすまんです。ヨドバシ、ネットショップの評価がえらくいいというなんかの記事を目にして納得。
いまの無線ルータ、当世風に言うと「Wi-Fiルータ」ですか。使い始めてから7年あまりになります。どこといって問題ないんですが、でもそろそろ考えたほうがいい。
たまたま「よかったら使って」とPlalaから貸してもらった(なんでだろ?)ルータがしまい込んであり、偶然ながら同型の機種。NECの WG1200HS3 です。高価ではないですが十分かつ満足で、想像ですが非常に優れたWi-Fiルータだったんじゃないかな。それで当時のPlalaも大量に保有していたとか。たぶん。
ま、そういうわけで豪華なことに予備のWi-Fiルータがある。しまっておいても劣化するだけでしょうし、そろそろ使ってあげようか。古いのが7年。今度のも7年ぐらい使えれば幸せです。
沖の光ルータ(NTT)に繋いだ形で「ブリッジモード」です。つまりルーターの機能は使わず、単なるWi-Fi発信機として使う。ま、ハブですね。
 古いのを外して、新しいのを接続しました。それだけです。なーんも必要なし。で、PCとかスマホの新しい接続先を(パスワードいれて)書き換える。
古いのを外して、新しいのを接続しました。それだけです。なーんも必要なし。で、PCとかスマホの新しい接続先を(パスワードいれて)書き換える。
成功。しっかりスピードも出ています。VDSL(銅線)を介しているんで、これで十分な速度です。ただ機器の配置がすこし不自由。そのうちケーブルを長くしようかな。
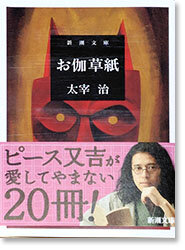 新潮文庫★★★★
新潮文庫★★★★ 交換作業。コード類をぜんぶ抜いて筐体を引っ張り出す。裏側をまるだしにして、念のためもう一度古いのを刺しなおしてみました。場合によっては3ピンプラグの
交換作業。コード類をぜんぶ抜いて筐体を引っ張り出す。裏側をまるだしにして、念のためもう一度古いのを刺しなおしてみました。場合によっては3ピンプラグの 「DVI→HDMIの変更によって
「DVI→HDMIの変更によって しかしこっちも必要なのは
しかしこっちも必要なのは たまたま出くわした解説サイトで謎が解けました。これは「わらべ唄」のアレンジだった。京の通り名を上から下にズラズラならべた唄です。たとえば「まるたけえびすに・・」は丸・竹・夷・二・・で、丸太町通・竹屋町通・夷川通・二条通・・。延々続いて最後はいちばん南の九条通で終わる。
たまたま出くわした解説サイトで謎が解けました。これは「わらべ唄」のアレンジだった。京の通り名を上から下にズラズラならべた唄です。たとえば「まるたけえびすに・・」は丸・竹・夷・二・・で、丸太町通・竹屋町通・夷川通・二条通・・。延々続いて最後はいちばん南の九条通で終わる。 で、ついネットッショップに頼ってしまいます。こういう行動が地元店舗を衰退させるんだなあと後ろめたさはあるものの、ま、しかたない。注文して翌日に届きました。1mのLANケーブル650 円、同じく1mのモジュラーケーブル210 円。ほんとはもっと安い品がいろいろあるんですが「送料無料」が心やましくて(
で、ついネットッショップに頼ってしまいます。こういう行動が地元店舗を衰退させるんだなあと後ろめたさはあるものの、ま、しかたない。注文して翌日に届きました。1mのLANケーブル650 円、同じく1mのモジュラーケーブル210 円。ほんとはもっと安い品がいろいろあるんですが「送料無料」が心やましくて( 古いのを外して、新しいのを接続しました。それだけです。なーんも必要なし。で、PCとかスマホの新しい接続先を(パスワードいれて)書き換える。
古いのを外して、新しいのを接続しました。それだけです。なーんも必要なし。で、PCとかスマホの新しい接続先を(パスワードいれて)書き換える。