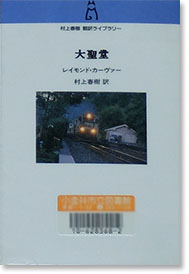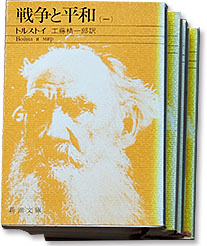★★★★ 文藝春秋
 太平洋戦争の真の責任者
太平洋戦争の真の責任者は誰だったのだろうというテーマです。ただし軍人をリストアップすると(当然のことながら)候補が多すぎるのであえて民間人に限定。さらにグググッと絞って
広田弘毅、近衛文麿、松岡洋右、木戸幸一の4人とオマケで
天皇。はて、彼らは有罪か情状酌量の余地ありか。
半藤一利がいわば検事の役割でまず難詰します。それを加藤陽子がなるべく弁護する。加藤陽子という人、文藝春秋なんかでよく活躍している歴史学者だそうです。日本の近現代史が専門。
で、内容ですが、想像していたとおりですね。まず広田弘毅は決して無実とはいえないようで、
戦争突入の責任がかなりありますね。半藤ジイさんは「広田って気分的には軍人だったんじゃないかな」。要するに城山三郎さんが「落日燃ゆ」でちょっと持ち上げすぎ。それほど見識ある人物じゃなかった。
次に近衛文麿は、まあ想像通り。天皇の前で足を組みかねないほどの格で、頭も切れるし実行力もあるはず。なのに、肝心な場面では何もしない。本人なりには構想があるらしいんですが、なぜか間違ったことばっかりやる。そしてすぐ逃げ出す。要するにお公家さんです。徳川慶喜みたいな部分もある。一見すごいのに結果が伴わない。
信念と覚悟がない。
定番の松岡洋右。みんなが非難するほど悪いやつではなかったかもしれない。悪名高い国連脱退も三国同盟も、
すべての責任を松岡にかぶせるのはすこし酷。性格が性格なんで誤解されるのも仕方ないし、実際天皇にも嫌われた。ま、だからといって同情すべきタマでもないようですが。
そして木戸幸一。私、この木戸についてはほとんどイメージがありませんでした。なんか静かな老人という雰囲気でしたが、写真をみたらだいぶ違いますね。ひそかに「野武士」と豪語していたらしい。木戸孝允の孫で役人出身で背が低くて天皇の側近で、
たぶん非常な策謀家。で、ゴルフばっかりしていた。
読み終えて感じたのは、当然のことながら人物も動きもグタグタ錯綜して、
時代は複雑怪奇だったんだなあということ。軍部が独走して政治家が小心で、だから戦争になった・・・なんて簡単な話にはならない。
たとえば
外務省の主流は対米強硬派で、日米交渉にあたった野村吉三郎を邪魔し続けた。周囲や部下が妨害して交渉がうまく運ぶわけがない。一時期ですが、陸軍よりも海軍よりも外務省が強硬だったこともある。また新聞も雑誌もいい気になって行け行けドンドン囃したてて、軍も政府も迷惑するほどだった。ただし末期になると、逆転して締めつけの対象になったけど、身から出た錆。だからこの連中が「
過ちは二度と繰り返しません」なんて言っても、けっして信じないほうがいい。
陸軍は皇道派と統制派が争い、政府にとって実は「
陸軍の対ソ強硬派がムチャするんじゃないか」がいちばん心配だったらしい。もしソ連がシベリアから軍を西に移動させる動きになったらすぐドンパチ始まったかもしれない状況だった。ということで陸軍の強硬な北進論を中和させるために、政府は南進論を許容した。結果的に両論併記。もちろん最悪です。
そうそう。日本の方向を決めてしまった感のある三国同盟ですが、あれの本質はドイツと組むというより「
英国が負けてからの戦後処理」にあった。太平洋、東南アジアから英国が撤退したあと、ドイツと権益を争うのはまずい。そこをスンナリさせるための同盟だった。ま、そういうタヌキの胸算用が三国同盟。要するに「カネメでしょ」が本筋。
開戦までの間、実は中国から手をひいてゴタゴタをおさめる機会は何回かあったようですが、常に問題になったのは「英霊に申し訳ない」。要するに賠償金なりなんなりの
お土産が得られるかどうかです。お土産ナシじゃ引っ込みがつかない。近衛や天皇までそういう気分で、少し景気のいい状況にしてから和平を提案しようという構想。みんなそういう考えなので、ズルズルズルズル続いてしまった。それでも昭和16年の11月初めまではまだ戦争を避ける道筋がかろうじてあったらしい。
軍人、政治家、役人、みんなが勝手な構想を描いて、勝手に動く。けっこう情報も握っていたんだけど、いろいろ思惑があるため握りつぶして共有しない。みんな少しずつ度胸がなかったり、少しズルかったり、意志が弱かったり、勘違いしていたり。
そうした「スベテ」の結果が12月8日開戦であり、4年後の敗戦につながった。
それはそれとして、読み終えて「こいつが一番悪い」と感じたのは木戸幸一ですね。目立たないけど、暗躍している。
木戸幸一。天皇という
いちばん肝心な部分の情報ルートの玄関番をやって、情報栓を恣意的に調節していた。本人的には「すべてお上のため」なんでしょうが、なんか動きが常に怪しい。で、そうした情報操作や組織・人事は後になってものすごく効いてくる。東條英機なんてのを引っ張りだしたのもやはり木戸幸一。キーマンでした。ちなみに東條英機は単なる生真面目で融通のきかない人間のようです。重要な時期に重要な地位につけてはいけない官僚軍人の典型。
長くはないけどなかなか面白い本でした。
これと一緒に莫言の「酒国」、賈平凹の「廃都」も借り出してたんだけど読みきれず。暑さでボーッとしているうちに期限がきてしまった。またの機会を待つか。
 KADOKAWA★★★
KADOKAWA★★★